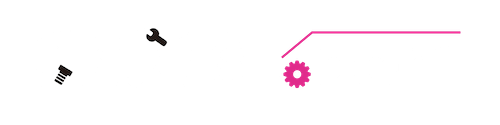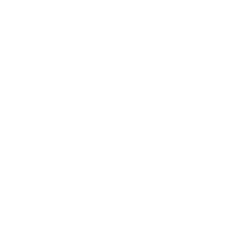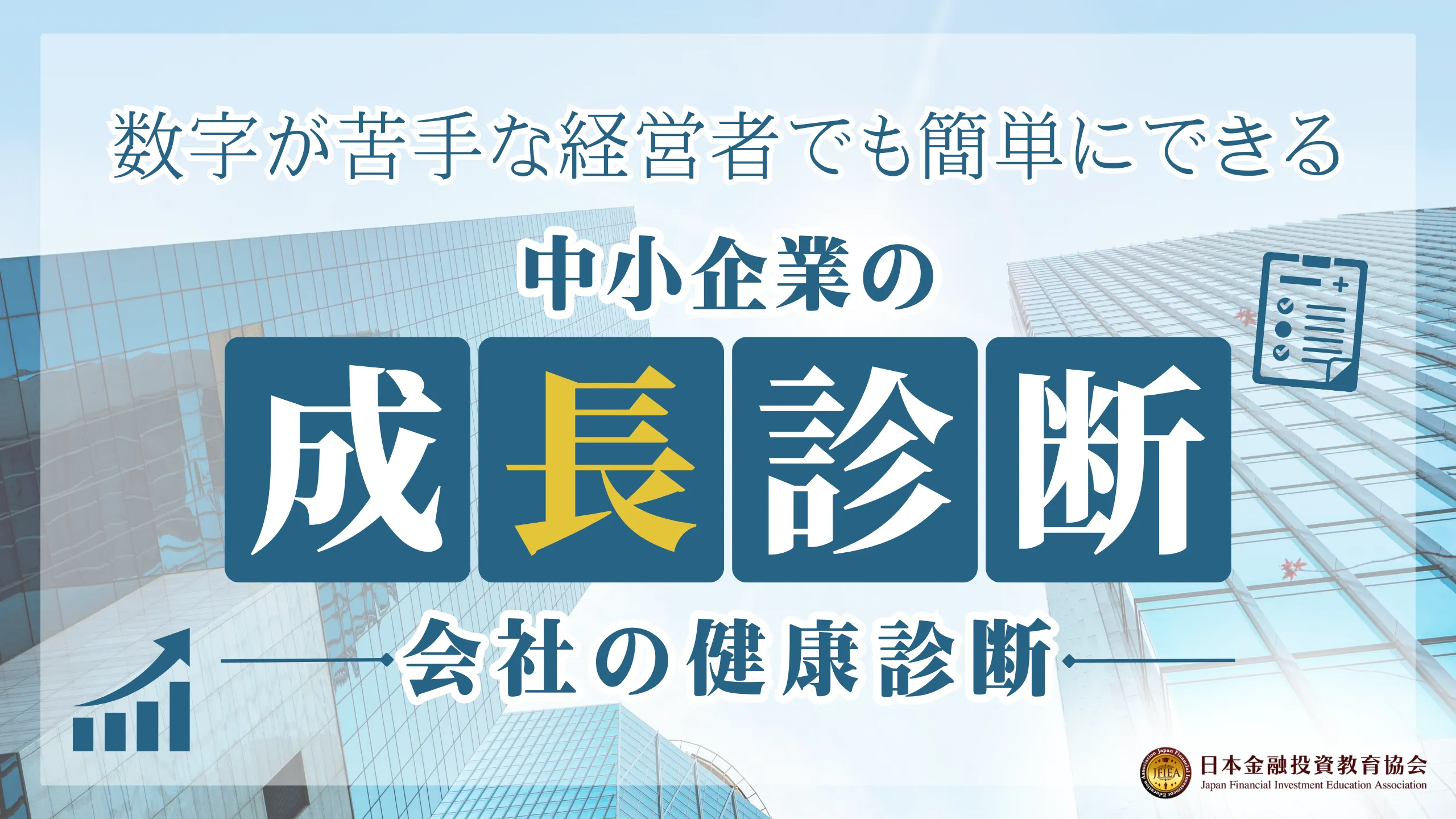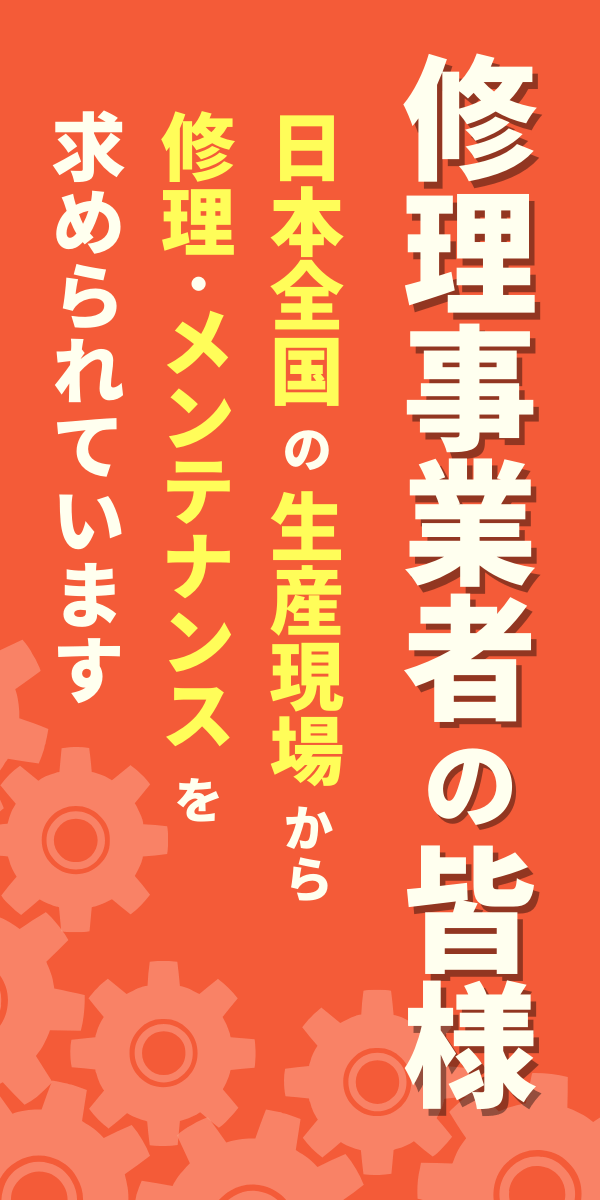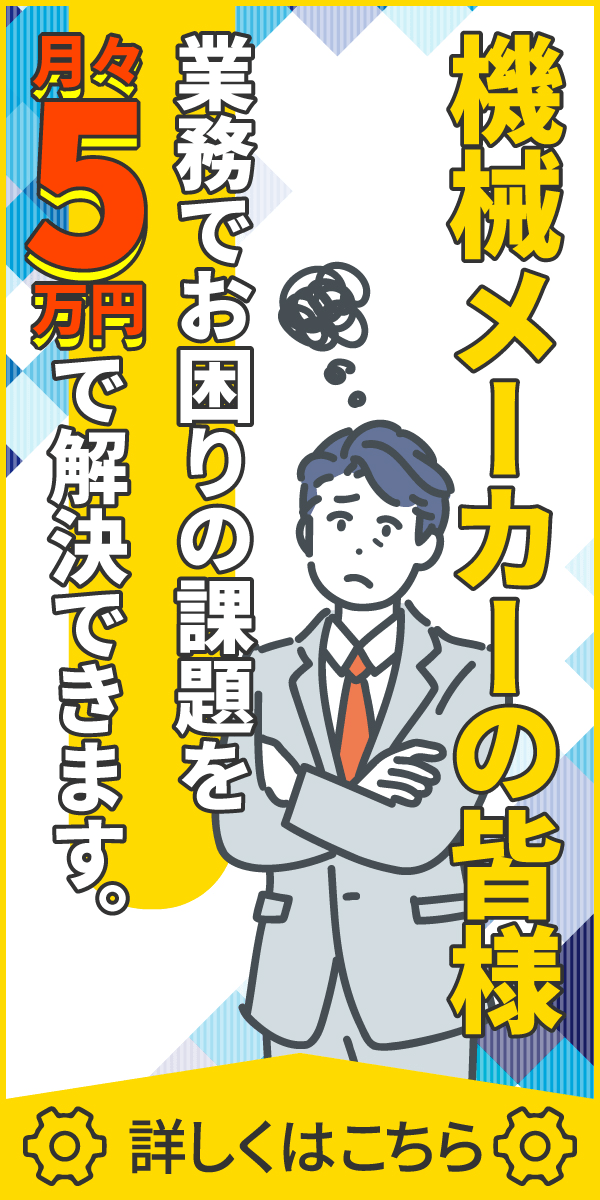AIが“水の異変”を聴き取る ― 衛星データ×FAST-Dで進化する漏水検知技術

Hmcomm株式会社は、滋賀県守山市で進めている「衛星データ×FAST-Dによる漏水検知システム」の実証実験について、次フェーズの方向性を正式決定しました。
衛星データとAI異音検知技術を組み合わせることで、広域リスクの予測とピンポイント漏水検出を両立する新たな社会インフラDXの形を目指します。
出典: PR TIMES(2025年10月24日)
※内容は再構成・要約のうえ独自の分析を加えています。
従来の点検を“聴く”AIが補完
水道の漏水は、地中で進行し、地表から目視できないケースがほとんど。
従来は「熟練作業員が地面の音を聴き分ける」という聴音調査が主流でした。
HmcommのAI技術「FAST-D(Fast Anomaly Sound Technology for Detection)」は、この聴音技術をデジタル化。
現場マイクが拾う音波をAIが解析し、
- 「水の流れ方の異常」
- 「圧力の変化」
- 「周囲ノイズとの違い」
をリアルタイムで識別します。
これに衛星の地表情報を統合することで、人が気づけない地下漏水の兆候まで捉えられるようになります。
実証実験の進展:守山市でのデータ構築
同社は守山市で、配水管台帳や修繕履歴と照合しながら、
- 地上マイクによる音響データの収録
- 衛星データとの相関解析
- 実際の漏水事例に基づくAI学習データセット構築
を進めてきました。
この取り組みで、AIが漏水の「音の特徴」を自律的に学習する基盤が整い、今後の本格運用に向けた精度検証フェーズに移行しています。
2段階のシステム構成
1️⃣ 広域漏水リスク特定フェーズ
衛星データや地理空間情報をもとに、リスクスコアを算出。
自治体単位での「漏水リスクマップ」を生成します。
2️⃣ ピンポイント漏水検知フェーズ
FAST-Dが現場音を解析し、AIが漏水箇所を高精度に特定。
地表面下のわずかな変化も検出できるよう設計されています。
この2つのフェーズを組み合わせることで、「地図で全体を把握し、AIで局所を確定する」仕組みが完成します。
機械修理ドットコム視点
設備保全が“データで診る時代”へ
① 聴覚から“データ保全”への転換
従来の点検では、人の耳や経験に頼ってきた領域をAIが支援。
熟練技術者の聴覚判断を数値化し、属人化の解消と継承の自動化を実現します。
② 地上+衛星のハイブリッド保守
衛星情報により「どこを点検すべきか」が明確になるため、点検ルートや人員配置の最適化が可能に。
これにより、維持管理コストの削減と作業負荷の平準化が期待されます。
③ 修理・点検のDX化モデル
AIが異常検知を行い、クラウド上でアラートを発報する――
こうした仕組みは、水道だけでなく、プラント・ガス・熱供給設備などの分野にも展開可能です。
現場の修理担当者は、今後「AIと共に診断する」時代へ移行していくでしょう。
今後の展開:自治体DXモデルへの発展
守山市での成果を基に、Hmcommは全国の自治体へ本システムの展開を検討中。
少人数でも持続的に運用できるインフラDXモデルとして、水道だけでなく、道路・橋梁・下水など、他の社会インフラにも応用が可能です。
まとめ
「衛星データ×AI音響解析」というアプローチは、人の五感を補完し、“見えない劣化”を先に察知する技術です。
この進化は、点検・保守の現場を「反応型」から「予測型」へと変えていくでしょう。
機械修理ドットコムとしても、このようなAI×センシング技術が現場の安全と効率を両立させる鍵になると見ています。