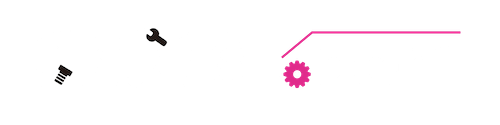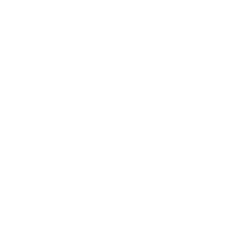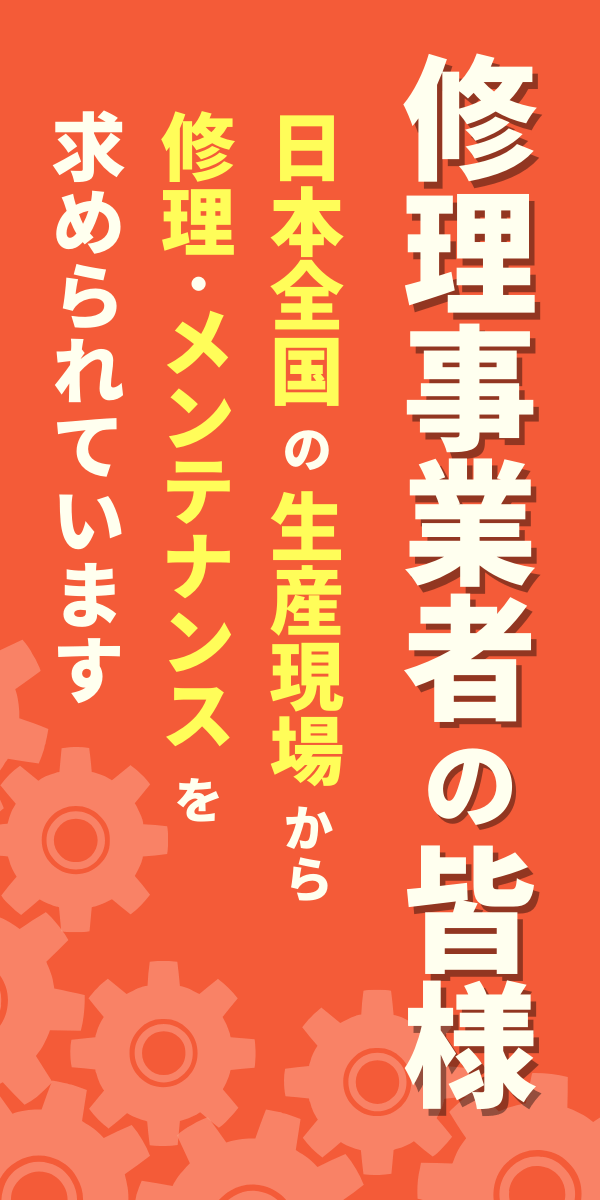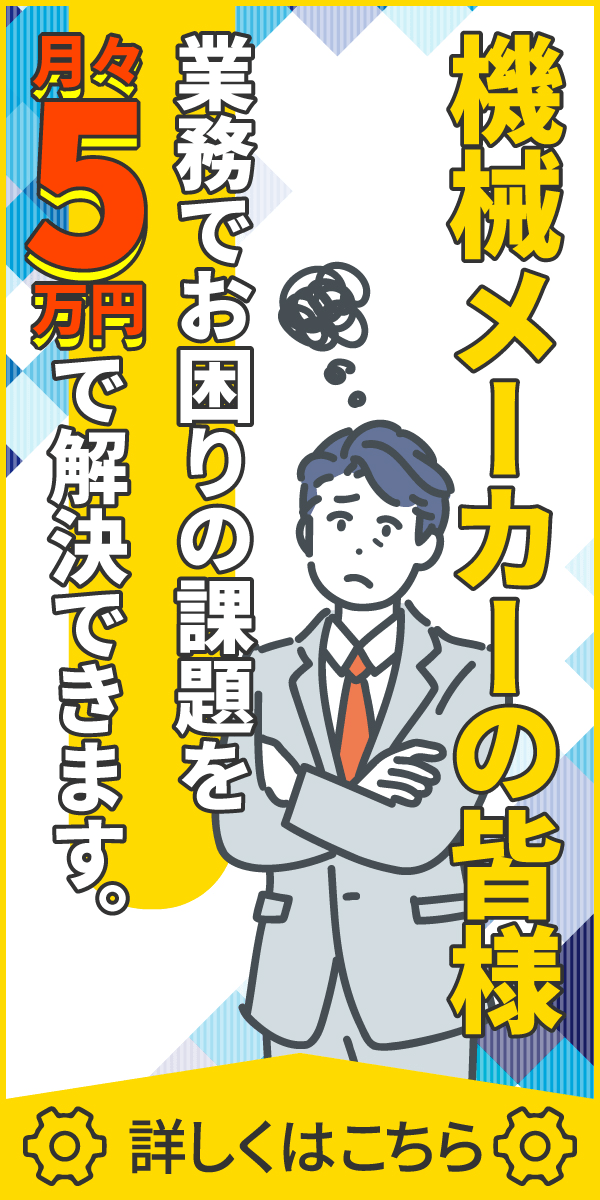設備保全の現場で進む「人材×DX」改革 ― 日本プラントメンテナンス協会が示す最新動向

公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会(JIPM)は、2025年9月に「2024年度メンテナンス実態調査報告書」を発表しました。
この報告書は、全国169社の製造業を対象に、設備管理や保全の実態、人材課題、DXの導入状況、カーボンニュートラル(CN)対策などを多面的に分析したものです。
出典: PR TIMES(2025年10月27日)
引用:2024年度メンテナンス実態調査報告書 ©公益社団法人日本プラントメンテナンス協会(2025)より要約
※内容は再構成・要約のうえ独自の分析を加えています。
現場で進む「人に頼らない保全」への移行
調査によると、約7割の企業が「設備保全の難易度が上がっている」と回答。
背景には、人材不足と高経年設備の増加があります。
最も重視されている施策は、
- 高経年設備への対応(66%)
- 人材育成対策(60%)
この2つが保全現場の最重要課題として挙げられています。
一方で、「現場活動」や「基本事項の整備」といった従来型施策の比重は低下しており、“属人化から仕組み化へ”という流れが明確になっています。
DXが支える「人材確保」と「作業の平準化」
報告書では、人材定着や採用難に対して、次のようなデジタル施策が効果を上げていると指摘されています。
- 情報技術によるムダの削減(41%)
- 自動化による業務の平準化(29%)
- デジタル発信を活用した採用活動(25%)
これらは単なるシステム導入ではなく、「保全業務をデータで見える化し、スキル差を補う仕組み」として評価されています。
機械修理ドットコムの視点から見れば、これは「熟練技術の形式知化」とも言えます。
ベテランの経験値をAI・IoTで再現する動きは、現場の安全性と継続性を高めるカギとなるでしょう。
保全費の動向 ― 「予防保全」が増加、予知保全は伸び悩み
興味深いのは、保全費の構成が変化している点です。
2024年度の予測では、
- 予防保全費用:+2.4%増加
- 予知保全費用:−2.1%減少
とされています。
IoTやAIの活用が進む一方で、実際には計画的な予防整備へのシフトが強まっているのです。
これは、AI診断やセンシング技術を導入しても、最終的な判断は「現場の人間が下す」ケースが依然として多いことを意味します。
機械修理ドットコムでは、AI分析と人間の判断を融合させた「ハイブリッド診断型メンテナンス」の重要性を重視しています。
カーボンニュートラルと保全の融合 ― 設計段階からの見直しが進む
カーボンニュートラル(CN)への対応は、もはや「環境部門だけの仕事」ではありません。
調査によると、CN対策は
- 全社的に統一して実施(77%)
- 製造・保全部門が主導するケースが増加中
と報告されています。
特に注目すべきは、CN対策の実施ステージです。
「設計段階(購入設備)」での対策が最も高く、53%を占める。
つまり、設備のライフサイクル設計時点から省エネ・低炭素化を織り込む動きが主流になりつつあります。
また、76%の事業所が「電力消費量のモニタリングシステム」を導入しており、データを活用したCN対策が実務に根づいています。
現場から見た“これからの保全”
報告書から見えてくるメッセージは明確です。
- 人に頼らず、安全に設備を守る仕組みを作る。
- データとAIを活用し、判断の精度を高める。
- 設備導入段階からカーボンニュートラルを意識する。
機械修理ドットコムでは、こうした動きを単なる「デジタル化」ではなく、“メンテナンス文化の再構築”と捉えています。
まとめ ― 「修理から予防」へ、そして「予防から持続」へ
日本の製造業は、老朽化・人材不足・環境対応という三重苦の中で、着実に新しい保全の形を模索しています。AI診断やモニタリングはもちろん、人の力を活かした現場DXと教育体系の再設計が、今後の鍵になるでしょう。
機械修理ドットコムでは、最新のメンテナンス動向を踏まえ、企業の「修理力」から「持続力」へと進化させるサポートを続けていきます。