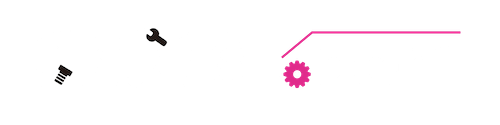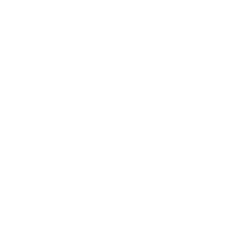異音の発生した機械の状態判断と修繕

今回は、異音が発生している機器の状態判断を含めたご相談をいただきました。
お問い合わせ内容は以下の通りです。
Q1.何が悪いのか
Q2.緊急性はどの程度か
Q3.きちんと直るのか
まずは、修繕前の動画をご覧ください。
かなり大きい異音で、機器から10mくらい離れた場所からでも、はっきりと異音が聞こえます。
そして、軸封付近に接近したシーンでは「カリカリ」や「シャカシャカ」といった、金属を逆なでするような高周波の音が入ってます。
これは、ベアリングの使用限界が近づくとよく発生する、特異なリテーナー音です。
通常、この大きさの機器に入っているサイズのベアリングでは、正常時に聞こえることはほぼないのですが、大きなベアリングでアンギュラベアリングだった場合は、正常時でもリテーナー音は聞こえます。
そのため、大きなアンギュラベアリングでは、しばしば、砲金のもみ抜き仕様のリテーナーが採用されます。(リテーナー音を解消するため)
テクニカデベロップメントでは、聴診棒で聴診し、さらに診断機を使って数字で裏付けを取る体制も整っていますので、機械の状態を詳しく判断することができます。
機器の状態を正確に判断し、コストとのバランスの中で、的確な修繕内容をご提案します
さて、今回のご相談の回答は以下のようになります。
ベアリングの経年劣化による不具合です。
直近(1週間~1か月以内)を推奨します。
直ります。
これ以上異音と振動が大きくなってくると、ベアリングの交換だけでは直らなくなるため、早期の修繕が必要となりますが、現状ではベアリング以外の部分まで影響が及んでいるほど振動が大きくないため、部品の交換で直ります。
ただし、この状態からさらに運転時間を増やしていくと、ベアリングのハウジングが削れてしまい、ベアリングを交換しても初めからがたつきが発生してしまいます。
非常に高価で更新費用も多大な機械では、ハウジングの交換やハウジングの修正も可能ですが、対価費用を考慮すると、この場合では機器更新の方が格段に安く仕上がるというのが正直なところです。
しかし、もし機器更新をしないのであれば、早期の修繕が必要不可欠となります。
今回は当社の判断を信用していただき、分解整備のご依頼を受けました。
どちらも、封入グリスが流出してしまい、内部の潤滑が滞っている状態です。
指で内輪を回してみると、「がりがり」「ごりごり」といった感触があり、これが機器の振動につながっています。
ハウジング状況
赤枠内に点在する黒い斑点のようなものが進行すると、ベアリングの外輪の幅で削れてしまいます。
通常、産業機械のハウジングの許容勘合値は0.05mm以内と言われており、これより穴サイズが広がってしまうと、ベアリングが正常でも異常振動が発生します。
異常振動がある回転機械は短命となりますから、ここはとても重要なところです。(メーカーや団体の規定により0.03mm以内としている事もあります)
この機器は、私たちの読み通りハウジングの穴がまるまる広がるほどの損傷はなかったため、再使用可能でした。
もしこの黒い斑点が進行すると、フレッチングという現象に進行します。
振動を伴う摺動を継続的に受けていた場合、腐食したような損傷を受けた状態がフレッチングです。
さらに進行すると帯状に削れ、前述のように使用不能となります。
交換部品一式
そして、組み立て後の試運転を撮影した動画です。
もちろん、マイクレベルなどは修繕前の動画とすべて同条件で録画しています。
このように機器の状態を把握して、必要な部分のみで修繕していくことは、トータルコストやランニングコストの圧縮にも繋がります。
状態を正確に判断し、コストとのバランスの中で、いかに的確なタイミングと内容で修繕をおこなうかが重要だと思います。
その判断は、公共施設の大きな機械の定期健診などを行っている実績からのフィードバックが大きく関与しています。
テクニカデベロップメントでは、単一の該当機の何年にもわたる数値の推移から、「整備の時期と内容の決定」、「分解時の部品の状態確認」、「組み立て後の試運転」までをおこなう業務を積み重ねてきました。
そのような経験が、今回の状態判断を可能にした礎となっていると考えています。